
公式サイト
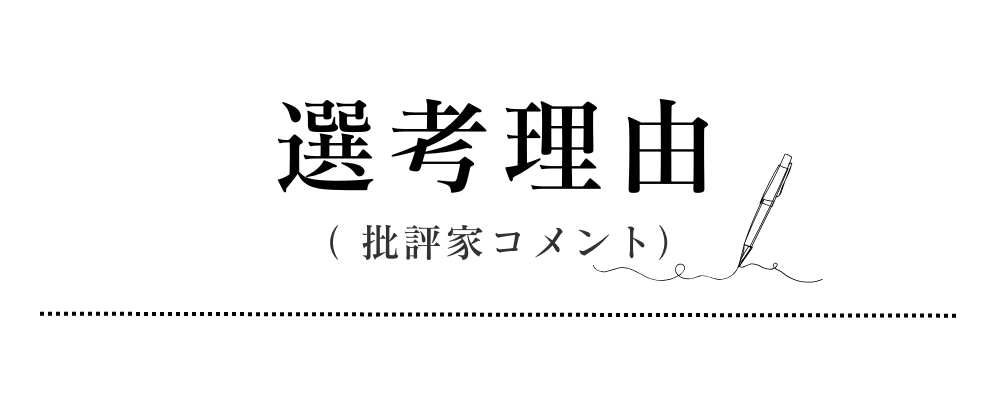
日本映画発祥の地である京都。そこにはまた「日本のハリウッド」と称され、草創期から日本の劇映画を支えてきた太秦という撮影所の聖地がある。かつて隆盛を極めた時代劇は、この太秦でその多くが生み出されていた。
そして東映株式会社が生まれた翌年、1952年にこの地で東映京都撮影所に発足したのが「東映剣会」。殺陣技術集団である。
70年を超える東映剣会の歴史を紐解いてみると、まさに「武士の本分」をみるような思いが去来する。以下は、とある武術家の宗師から聞いた印象的な言葉である。
〜 戦うことが武士の本義。武士は戦うことで家族を、国を、義を守る。そのためには「常在戦場の備え」がもっとも必要なことである 〜と。
時代が変われば社会も人の嗜好も変化する。東映もまた移り気な世間が望むエンターテインメントを、時流にあわせ世に送り出し続けてきた。時代劇映画からテレビ時代劇、任侠やヒーローものといった具合に。
そのなかでもまさに底辺からプロダクションを支え続けてきたのがこの東映剣会である。ただただ、彼らは常に備え、自らを鍛え、そして様々な方法で役者たちの動き(アクション)を演出しながらも、常に殺される“斬られ役“に徹してきた。手に持つのは日本刀から拳銃、殴りあいのシーンまで実に様々。作品に合わせ繰り出される、その手数の幅の広さには本当に驚かされる。寡黙に役者をたてる彼らの姿は、自らの本分を全うする武士そのもののようだ。
剣会としては、本筋の時代劇は冬の時期が長く続いたかもしれない。しかし近年、時代劇と現代劇をマッシュアップしたり、新しいタイプの時代劇の息吹を感じさせる作品が生まれたりしている。
日本映画界には、この流れがさらに発展してほしいと切に望む。そしてまた、時代劇の伝統を次世代に引き継ぐような、ちゃんばらの良さを堪能できる作品にも期待したい。
かつての先達たちもアイデアを出し合い、時代と共に観客を魅了する作品を生み出してきた。温故知新に見方を変えれば、時代劇は可能性が溢れるブルーオーシャンではないだろうか。
(日本映画批評家大賞機構事務局)
