
公式サイト
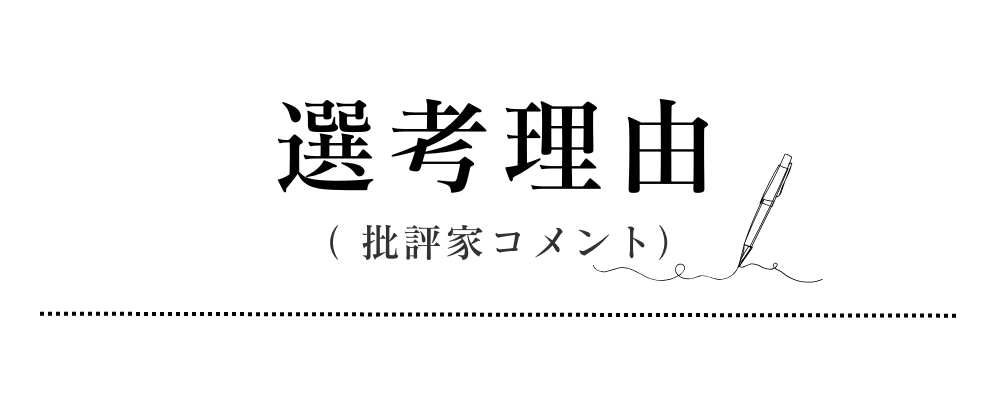
米アカデミー賞では、近年、マイノリティを主人公にした作品を意識的にノミネーションさせている。白人が主人公の作品が多い映画史の偏りを減らす為と、多様な世界を描くことの重要性に気づいたからである。確かに日本映画界もマイノリティに目を向けることを今まで怠っていた。そんな中、『ぼくが生きてる、ふたつの世界』は、本腰を据えてろう者とコーダの存在を綴った日本映画初の作品といえよう。
ろう者はすべて当事者の俳優。きこえない親を持つコーダの青年役を吉沢亮が演じ、トレーニングで習得した手話で家族やきこえないの人々と語らうシーンが多々ある。またコーダ作家による原作を映画化する上で、手話演出者、コーダ監修者が入り、手話監修協力として全日本ろうあ連盟が製作に参加している。ここまで徹底した「正しい表現」での映画製作もさることながら、いち家族の成長物語として多くの観客に自分事として感情移入させる描写の連続に心奪われた。
物語の前半、ろう者の夫婦が子どもを授かるも、きこえないことで幼児の危険を察知できない事象が映し出される。それを補うのが祖父母なのだ。やがて小さな息子は車のクラクションに気づかない母親の手を引っ張るようになり、成長とともに当然のように母親の通訳として日常を過ごす。その子役達の演技にも釘付けだった。思春期からを吉沢が演じ、気づいて貰えない怒りを母親にぶつけていくのだ。このような母と子のギクシャクとした関係を見つめていたら、自分の両親や我が子の子育て期に思いを馳せ、胸が熱くなった。これが本作を万人に支持される作品へと昇華させた最大の要因だろう。
この映画では多くのマジョリティである観客に、ろう者の世界を体感させようと音の演出もなされている。確かに同じ場所でもきこえる人ときこえない人では世界が違う。それを無音のシーンを作ることで観客に擬似体験させるのだ。作品の素晴らしさとは、俳優の演技、監督の演出、各部署とのチームプレイの結果だと個人的には思っている。そこを踏まえた上で、本作はスタッフすべての熱量をスクリーンから存分に浴びる愛の塊のような映画であった。
(伊藤 さとり)
